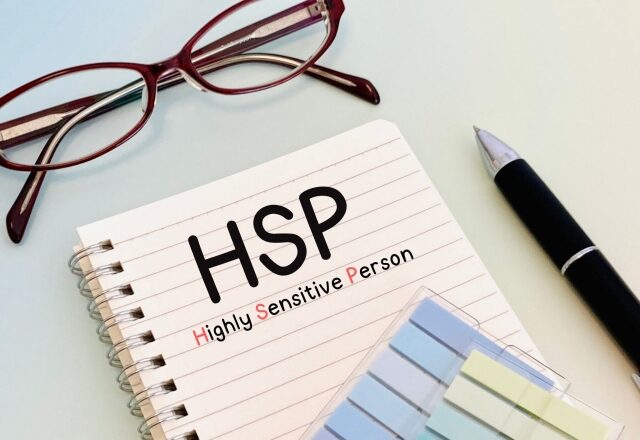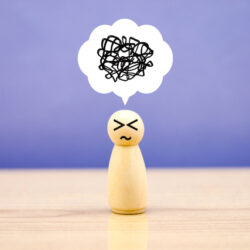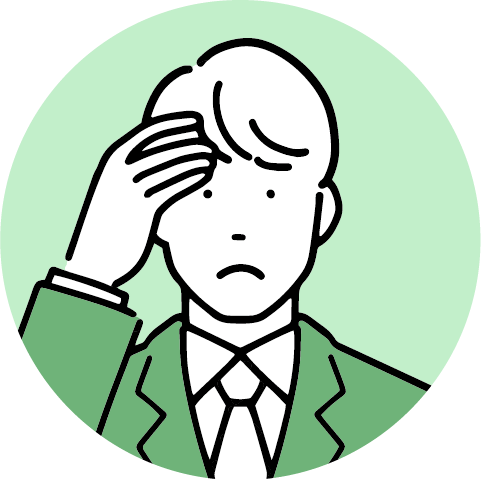
「今の職場で働くのがつらい…私が弱いだけ?」
「HSPで仕事が続かないって甘えかな…?」
あなたはHSPを抱えて働くことで悩み、このように自分を責めてしまうことはありませんか?
HSPの繊細さは長所でもありますが、仕事で困りごとを抱える原因になることもあります。仕事が続かないのは、決してあなたが悪いわけではありません。
本記事では
- HSPとは何か?
- HSPの4つの特性
- 働くのがつらい、怖いと感じる原因・シチュエーション
- 無理なく働くためのポイント
- HSPの方が利用できる支援・相談窓口
を解説します。
あなたが自分のHSPの気質を理解し、安心して仕事をするためのお手伝いになれば幸いです。
そもそもHSPとは?

HSPとは、「感受性が強く敏感な気質を持った人」を指す言葉で、「Highly Sensitive Person(高度に感受性が高い人)」の頭文字から「HSP」と呼ばれています。アメリカのエレイン・N・アーロン博士によって提唱された概念です。
人は生まれてから死ぬまで、家庭や地域、文化など、様々な環境から影響を受けます。しかし、同じ環境でもどれくらい影響を受けやすいかは個人差があります。この環境は音や光などの物理的なものに限らず、心理的・社会的なものも含まれます。
このような広い範囲の環境に対する感受性は「環境感受性」と呼ばれます。HSPの方はこの「環境感受性」が相対的に高い方です。
環境感受性(HSP)を専門とする心理学者2名によって企画・運営されるHSP情報サイト「Japan Sensitive Research」によると、環境感受性は、
「ポジティブおよびネガティブな環境に対する処理や知覚の個人差」として定義される概念引用:Japan Sensitive Research 心理学者によるHSP情報サイト
と記述されています。
この項目では、HSPがどのようなものか、詳しく見ていきましょう。
HSPは病気?
HSPは病気や脳の問題ではなく、環境に対する感受性の個人差によるものです。
簡単に言えばその人の「性格」「気質」のようなものです。病気ではないので、HSP自体には医学的な治療法はありません。
HSPを提唱したアーロン博士の著書「The Highly Sensitive Person」によると、人口の約15~20%、つまり「およそ5人に1人」はHSPの気質があるとしています。例えば、30人の職場なら、およそ6人は同じ気質を持った仲間がいる計算になります。
この意見は考え方の一つではありますが、HSPは珍しいものではないと言うことができるでしょう。
そして、感受性の高さはその人の個性であるため、決して「治さなければならないもの」でもありません。
しかし、環境に対する感受性が高いために、合わない環境にいた結果、仕事や日常生活に悪影響が出たり、ストレスによる胃腸炎やうつ病のように身体的・精神的に影響が出たりするなど、マイナスに作用する場合があります。
もし、あなたが憂鬱な気分や無気力感を抱え生きづらさを感じているなら、「そういう性格だから」と放置せず、早めに精神科や心療内科を受診しましょう。
HSPの世界の見え方
HSP自体はあくまで気質であり、病気ではありません。
しかし、その敏感さからうつ病や適応障害になり、精神科を利用される方もいらっしゃいます。
HSPの概念を提唱したアーロン博士によるサイト「The Highly Sensitive Person」では、HSPの方は下記のような傾向があるとしています。
- まぶしい光や、強い臭い、肌触りの悪い布、近くを通るサイレンの音といったものに容易に圧倒されてしまう。
- 短時間に多くのことを抱えるとあわててしまう。
- 暴力的な映画・テレビ番組を見ないようにしている。
- 忙しい日々が続くと、ベッドや暗い部屋、もしくは一人になって刺激をやわらげることができる場所に閉じこもりたくなる。
- 生活する上で、動揺したり圧倒されるような状況を避けることを最優先にしている。
- デリケートで繊細な、香りや味・音・芸術作品がわかり、それを楽しんでいる。
- 豊かで複雑な内面世界をもっている。
- 子供のころ親や先生は、わたしのことを繊細あるいは内気だと思っていた。
環境からの影響を受けやすいため、強い刺激を避けようとする傾向にある事がわかります。
あくまで傾向であるため、HSPの方すべてに当てはまるとは限らない点には注意が必要です。
HSPの特性
HSPの方は特徴的な4つの特性「DOES」を持っている傾向があります。
- D:Depth of processing/深く考えられる
- O:Easily Overstimulated/過剰に刺激を受けやすい
- E:Emotionally reactive/感情の反応が強く、共感力が高い
- S:Sensitive to subtle stimuli/些細な変化を察知しやすい
これらの特性にすべて当てはまる方がHSPだとは限りませんが、可能性は高いでしょう。
HSPは病気ではないので、はっきりとした医学的な診断基準は存在しません。しかし、自分の傾向を知る手段の一つに、イルセ・サン(著)『鈍感な世界に生きる敏感な人たち』を元にしたHSP診断簡単セルフチェックというものがあります。確実な診断を出すものではないですが、参考程度にチェックしてみると良いでしょう。
HSPがつらいと感じること
HSPは、良くも悪くも「環境からの影響を受けやすい」と言われています。良い影響を与える環境に身を置いていると、良い結果が得られやすく、悪い影響を与える環境にいると、悪い方向に進みやすい傾向にあるのです。
そのため、周囲の状況や雰囲気に振り回され、仕事や社会生活でつらさを抱える場合があります。
例えば、職場がポジティブな雰囲気だったり、相手が笑顔で話してくれたりすると、高い感受性でその場の空気や感情を読み取って、自分もポジティブな気分になったり、人にやさしく接することができます。
逆に、誰かが怒られていたり、ピリついた空気が流れていると、それをすぐに察知して、自分が怒られているように感じて落ち込んでしまったり、周りが気になって仕事に身が入らなかったりします。
環境から影響を受けることは誰にでもあることですが、HSPはそれがより顕著であると考えられています。
外から受ける刺激や、周囲の状況によって、疲れを感じやすく、それが仕事でのつらさにつながってしまう傾向があります。
HSPで仕事が続かないのは「甘え」か?

「病気ではない」とはいえ、ちょっとしたことで環境に振り回されるのがつらいのは当たり前です。自分に合わない職場環境のために、すぐに職場を辞めてしまった、という経験がある方もいるでしょう。
それは決して甘えや弱さではありません。
あなたの繊細さは、他の人より鋭いアンテナを持っているようなものです。雰囲気の悪い職場に居れば、悪い雰囲気を察知して心が疲弊し、「仕事を辞める」選択肢を選んでもおかしくありません。
むしろ、悪い環境から離れ、より良い環境を追い求めることは、HSPの気質がある方にとって、必要なことだとも捉えられます。「流されやすい」ことは良くないイメージを持たれやすいですが、良い環境で良い方向に流されれば、悪いことはありません。
働く中でどうしてもつらく、「この環境は自分にとって良くない」と判断できるなら、環境を調整するために「仕事を辞める」選択肢も大切な過程の1つだと言えるでしょう。
働くのが怖い原因|HSPの特性と仕事の食い違い

HSPには「DOES」という4つの特性がある事をお伝えしました。これらの特性は、うまく使えればあなたの長所となり得ます。
しかし、多くの人が働く環境ではこの個性が「仕事との食い違い」を生み、悪影響を及ぼすことで、つらさの原因になることがあります。
この項目では、「DOES」の特性がどのように仕事のつらさにつながるのか、仕事での苦手なシチュエーションとともに解説します。
D:物事を考えすぎて行動が遅れる
HSPの方は物事を深く考えてから行動する傾向があるため、スピードが求められる業務では「考えすぎ」になりがちです。
他の人が行動を優先して動ける場面でも、あらゆるリスクや可能性をシミュレーションしてからでなければ次の一歩が踏み出せないことがあります。
この慎重さは長所になりますが、「とにかく数をこなす」「スピードが重要」とされる仕事とは相性が悪いと考えられます。
急な仕事の依頼やマルチタスクが求められる業務が多い職場だと、脳がパニックに陥ったり、それぞれのタスクがなかなか進まない状態になってしまう恐れがあります。
O:刺激を過剰に受けやすく、オープンなオフィスが苦手
HSPの方は些細な音や光、匂いなどの刺激を受けやすいです。以下のように外部からの刺激が多い場所では、その環境に居るだけで体力を消耗してしまう可能性があります。
- 電話の呼び出し音
- 同僚がキーボードを叩く音
- 蛍光灯のちらつき
- 誰かの強い香水の匂い
など
1つひとつは小さな刺激でも、それが1日中続くと気づかないうちに疲れ切ってしまいます。
HSPにとって雑音や人の出入りの多い職場は、安心して仕事ができない要因となる場合があります。
特に、電話や雑談が飛び交うオープンなオフィスは、「刺激の洪水」の中にいるような感覚となり、集中力を奪われる恐れがあります
E:感情への反応や共感力が強く、人間関係が負担になる
HSPの方は共感性が高いために、他人の感情に強い影響を受けやすく、人間関係で心をすり減らしてしまう傾向があります。
相手の表情や声のトーンから「今機嫌が悪いのかな?」「もしかしてがっかりさせてしまったかも…」と敏感に察知し、気を遣ってしまうことも珍しくありません。
自分と直接関係のないことでも、自分のせいだと感じてしまうことがあります。職場で機嫌の悪い人がいるだけでも、ドキッとして過剰に配慮してしまうことで、大きく消耗してしまうでしょう。
このような人間関係の悪い職場や、常に緊張感が漂う仕事は、HSPにとって大きな負担になる可能性があります。
S:些細な変化を察知して疲弊しやすい
HSPの方は相手の表情や言葉のニュアンスなどの些細な変化に敏感なため、考えなくても良いことまで深読みしてしまい、行動にブレーキをかけてしまう場合があります。
他の人であれば聞き流すような一言や、見逃すようなちょっとした仕草から、相手の感情を読み取る、感情の起伏に気づくなど、時に相手の本心を見抜く助けになることもあります。
しかし、ネガティブな方向に深読みしてしまうことも多く、仕事がなかなか進まない可能性もあります。
例えば、大勢の前でプレゼンや意見発表する場では、その場の一人一人の表情や反応、場の雰囲気を深く読み取ろうとして疲弊してしまうでしょう。また、発表前からうまく話せるのか不安になり、過度なプレッシャーを感じてしまっていることもあります。
HSPが今の職場で無理なく働くためには?試したい5つのポイント

自分のつらさはHSPが原因だったんだ、とホッとした方もいらっしゃるでしょう。
原因がわかったら、対策も立てやすくなります。今の職場であなたのつらさを和らげる方法も考えやすくなるでしょう。
この項目では、自分を守るための工夫を5つご紹介します。
自分の特性を理解する
HSPの方が無理なく働くためには、自分がどのような特性が強いか理解することが大切です。
ここまで様々なHSPの特性を解説してきましたが、どのような刺激に敏感なのかは人それぞれで大きく異なります。自分にとって必要な対策は何かを知るためにも、まずはストレスとなる要因を分析しましょう。
ストレス要因を知ることで、自分にとって最適な働き方についても考えられるようになります。
もしも一人で考えることが難しい場合は、医療機関やカウンセラーなど周りに相談しながら進めることもおすすめです。
物理的な刺激を減らす工夫をする
手軽にできるのは、五感から入ってくる刺激の量をコントロールすることです。
HSPが疲れやすくなる要因である刺激を意図的に減らすだけで、ストレスが軽減されます。
例えば、聴覚過敏で周囲の雑音が気になるのであれば、上司に許可を得て、ノイズキャンセリング機能付きのイヤホンや耳栓、イヤーマフを使ってみると良いでしょう。眩しさを感じやすいのであれば、PCモニターの明るさを下げたり、ブルーライトカットができるメガネを使ったりするのも有効です。
物理的な刺激を減らして、快適な環境を整えましょう。
不安を言語化する
頭の中で渦巻いている不安や心配事は、一度紙に書き出してみましょう。
HSPの方は物事を深く考えるために、不安を実際よりも大きく感じやすい傾向にあります。
何に不安を感じているのかを書き出すことで、「これは今考えても仕方ない」「これは上司に確認しよう」と、問題を切り分けることができます。書くだけで不安が解消されることもありますし、自分の考え方の傾向に気づけることもあります。
書くのが難しければ、勇気を出して誰かに話してみるのも良いでしょう。信頼できる人に聞いてもらうことで、頭の中が整理できますし、思ってもみない解決策が見つかることもあります。
人との間に「心の境界線」を引く
HSPの方は人の感情に影響されやすいため、自分の感情と相手の感情に、意識的に線を引く練習が必要です。
共感力が高いのは役に立つこともありますが、自分を守るためには適度な距離感を保つことも大切です。
上司の機嫌が悪くても、「上司は今機嫌が悪いんだな、でもそれは自分じゃなくて、上司自身の問題だ」と心の中で唱えてみましょう。
また、HSPの方は空気を読んでしまうために、頼まれたら断れないことも多いです。しかし、無理だと思ったら「少し時間をいただけますか?」「今は○○の作業で手一杯で…」など、断る勇気を持つことも境界線を引くことの1つです。
すぐにできなくても、「自分と他人は異なる」という意識を持つだけで、少しずつ楽になるでしょう。
1人でクールダウンする時間を意識的に作る
HSPの方は、職場の環境や人間関係でストレスを感じやすく、疲れやすい傾向があります。ストレスを抱え続けると、うつ病や適応障害などの精神疾患につながることがあるため、注意が必要です。
1日の中でほんの数分でも良いので、意識的に1人になり、脳を休ませる時間を作りましょう。HSPの方は音や光などによる刺激を受けやすいため、できるだけ刺激の大きな変化がない環境で脳をクールダウンさせることが必要です。
例えば、
- お昼休みは同僚とではなく、公園のベンチや空いている会議室など、1人で静かに過ごせる場所で
- 仕事の合間にトイレへ行く、個室で数回深呼吸する時間を取る
- 退勤後にカフェに寄り、ぼーっとする時間を作る
など
ほんの数分でも刺激から離れた時間を作ることで、午後の集中力や帰宅後の疲労感が変わることもあります。
合わない人と接した後に、自分を取り戻すためにも有効とされています。
HSPの方が向いている仕事は?

今の職場がどうしてもつらく、「新しい環境で働きたい」という場合もあるでしょう。環境を変えるとしても、以前と同じような仕事では、同じようなつらさを感じることがあるかもしれません。
この項目では、HSPの方が向いていると考えられる仕事の例を3つ紹介します。
静かな環境でマイペースに進められる仕事
HSPの方は外部からの刺激に敏感なため、そのような刺激が少なく、自分のペースで進められる仕事が良いでしょう。在宅勤務が可能な仕事も、自分のペースで進めるのに向いている可能性があります。
WebライターやWebデザイナーなどは、スキルが求められる分、一人でコツコツと仕事を進められるでしょう。
作業の正確さ、細やかさが必要な仕事
HSPの方は深く考えすぎる傾向や、些細なことに気づきやすい傾向があります。その特性が作業の正確性や細やかさが求められる仕事において、長所となるでしょう。
経理や事務、製造業での分析や検査などは、特に正確性を求められるため特性を発揮できる可能性があります。
人との関わりが少ない仕事
HSPの方は人からの影響を受けやすいため、他人との付き合いを苦手とする方もいます。そのような場合は、人と関わる機会が少ない仕事が良いでしょう。
こうした仕事には、倉庫での作業員や清掃員などが挙げられます。
仕事がつらい時に頼れる支援・相談窓口

「今の職場がどうしてもつらい」「新しい環境で働きたい」と考えている方もいるでしょう。そんな時、安心して働いていくためにサポートを受けられる場合があります。
この項目では、仕事がつらい時や、新しい環境で働きたいときに活用できる支援・相談窓口をご紹介します。
こころの耳
「こころの耳」は厚生労働省が運営する、「働く人のメンタルヘルス・サポートサイト」です。
働く方やそのご家族、事業者の方などに向けて、メンタルヘルスやそのケアに関する様々な情報や相談窓口を提供しています。
ストレスチェックやセルフケアなど、幅広い困りごとに対応しており、迷ったら悩みに合わせて適切なページに案内してもらえるチャットボットも設置されています。
電話だけでなく、メールやSNSでの相談が可能です。仕事に不安があるけどどこに相談すべきかわからないときなど、困りごとがある時に利用してみると良いでしょう。
職場の上司や同僚には相談しづらい悩みなど、仕事関連だけでなく、キャリアや生活に関する相談にも活用できます。
参考:働く人のメンタル・ポータルサイト こころの耳|厚生労働省
サポステ(地域若者サポートステーション)
「地域若者サポートステーション(サポステ)」は、15~49歳までの就業・就学中でない方を対象に、就職に向けた支援を行っている機関です。
サポステは無料で利用できます。専門スタッフによる面談や、働くために必要なビジネスマナーやコミュニケーションに関する訓練、就業体験、面接・履歴書の指導などの就職活動支援などを受けることができます。
ハローワークや福祉機関など、地域の支援機関や民間団体と連携を取っているため、総合的な支援を受けられます。就職するだけではなく、職場に定着するまでをバックアップしてもらえます。
WORK! DIVERSITY プロジェクト in 岐阜

「WORK! DIVERSITY プロジェクト in 岐阜」では、岐阜市内在住の「働きづらさを抱えている」岐阜市民の方を対象として、障害福祉サービスを提供し、就労支援を行う取り組みを行っています。
岐阜市内の「ダイバーシティ就労支援拠点」で、働き続ける力を身につけるための支援を、障害がなくても無料で受けることができます。「ダイバーシティ就労支援拠点」は、障害がある方の就労をサポートしている「就労移行支援事業所」や、サポートを受けながら働くことができる「就労継続支援事業所」です。
このプロジェクトは、岐阜市にお住まいで、HSPなどの働きづらさがあり働く前に支援を受けたい方で、障害者手帳をお持ちでない方であれば、誰でも利用できます。
障害者手帳が無くても利用できる手段の1つとして「WORK! DIVERSITY プロジェクト in 岐阜」への相談、利用を検討してみてはいかがでしょうか?
まとめ|HSPの方が働くのをつらいと感じる原因と働き続けるためのポイント
まとめ
- HSPは病気ではない。しかし、環境からの影響を受けやすく、仕事などで悩みやストレスを抱えやすい。ストレスによってうつ病や適応障害などを発症する場合もある。
- HSPの4つの特性「DOES」と仕事との食い違いによって働くことがつらいと感じる場合がある。
- 自身のHSPの特性によるものも含め、仕事で苦手なことや状況を知り、理解を深めることで、苦手への対策が立てやすくなる。
- 今の職場で働き続けるためにできる対策として、イヤホンなどで物理的な刺激を減らす、不安の言語化、人との心の距離感を保つ、意識的に1人になれる時間を作る、などが挙げられる。少し工夫するだけでもつらさを和らげられることがある。
- HSPの方は環境に左右されやすいため、良い環境であれば働きやすくなる。現在の状況が自分に合わないと感じるなら、転職など、職場環境を変えることも選択肢に。
- HSPの方が環境を変えて次のステップに進むための相談先として、「こころの耳」や「サポステ」などの公的支援が頼りになります。
同じHSPでも、その感じ方は1人ひとり異なります。大切なのは、他人と比べるのではなく「自分だけのHSPとの付き合い方」を見つけることです。
HSPは苦手なことが多いですが、「深く処理する」「些細な変化に気づきやすい」などの特性は、長所となり得ます。
この記事が、あなたの繊細さを活かすお手伝いになれば幸いです。
この記事に関するお問い合わせはこちらまで:workdiversitygifu@sus-sup.org