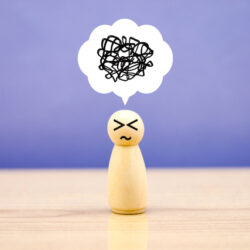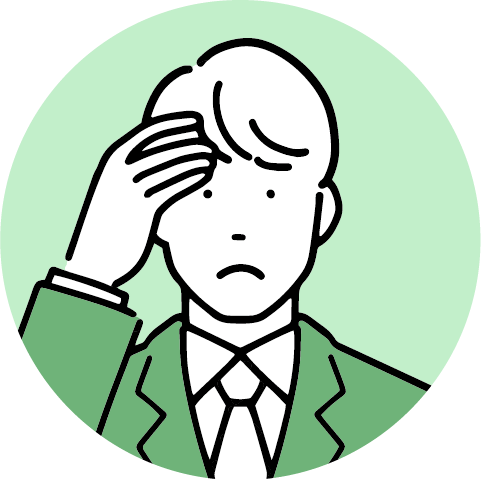
「周りの人のように、普通に食事ができない…」
「体型や体重のことが頭から離れず、仕事に集中できない…」
「本当はもっと頑張りたいのに、心と体がついていかない…」
など、1人で悩み、自分を責めてしまってはいませんか?
摂食障害を抱えながら働くことは、本当に大変なことです。
摂食障害は、単なる「わがまま」や「自己管理能力の低さ」ではありません。治療が必要な病気です。しかし、周りからの理解を得られにくく、職場で孤立感を深めている方も少なくないでしょう。
本記事では
- 摂食障害と仕事への影響
- 摂食障害を職場に伝えるべきか?
- 仕事が辛いと感じた時の選択肢
- 摂食障害の方が利用できる支援制度・相談先
について解説していきます。
1人で抱え込まず、自分に合った働き方を見つけるための一歩を踏み出してみませんか。
摂食障害とは?

「摂食障害」という言葉を聞いたことはあっても、具体的にどのような病気なのか、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
まずは、摂食障害の基本的な知識について理解を深めていきましょう。
摂食障害の種類と主な症状
摂食障害は、食事のとり方や食行動に著しい問題が表れ、心身に深刻な影響を及ぼす精神疾患の1種です。
主に、下記のように分類されます。
- 神経性やせ症(拒食症)
- 神経性過食症(過食症)
- 過食性障害
- 回避制限性食物摂取症
順番に見ていきましょう。
神経性やせ症(拒食症)
「太ることへの極端な恐怖」から、食事量を厳しく制限したり、全く食べなくなったりする状態です。明らかにやせていてもそれを異常と感じられません。
標準体重を大幅に下回る低体重であるにも関わらず、自分では「太っている」と思い込んでしまう「ボディイメージの歪み」が特徴です。
食事量を制限したり、過食嘔吐したりすることで低栄養状態になります。心身両面のケアが必要ですが、低栄養が進むほど治療が難しくなります。
低栄養状態になるため、下記のような身体症状・心理的症状が表れます。
- 身体症状
疲れやすい、寒がり・冷え性、食欲がない、下肢のむくみ など - 心理的症状
集中力の低下、仕事の能率の低下、イライラする、人との交流を避ける など
神経性過食症(過食症)
自分ではコントロールできないほどの強い衝動にかられて、大量の食べ物を一気に詰め込むように食べる「過食」を繰り返します。
過食した後に体重増加を防ぐために、意図的に嘔吐したり、下剤を乱用したりする「代償行動」がみられます。
症状が人前に出ないため、周囲が気づかないこともあります。自分では病気だと思わないこともあるため、治療を受けず、身体症状が進んだり、うつや不安が強まったりすることがあります。
- 身体症状
嘔吐が続くことで唾液腺が腫れる、歯の表面が胃酸で溶ける など - 心理的症状
体重次第で自己評価が変わる、気分の浮き沈み、うつ など
過食性障害
代償行動を伴わない「過食」を繰り返す状態です。この「過食」は単に食べ過ぎることではなく、短時間に大量の食べ物を食べることを指します。
神経性過食症と同様に、コントロールできない食欲に苦しみますが、嘔吐や下剤の乱用などはありません。ただし、体重が増える傾向にあり、肥満やメタボリックシンドロームにつながるリスクがあります。
また、ほかの精神疾患にもかかっていることが少なくありません。
回避制限性食物摂取症
食物摂取の回避・制限によって、必要なエネルギーや適切な栄養の摂取を満たすことができず、著しい体重減少、栄養欠乏、経口栄養補助食品や経管栄養への依存、健康障害や心理的な社会的機能に障害をきたすものです。
先述した神経性やせ症のような、体型や体重へのこだわりやボディーイメージの歪みはありません。
原因として下記のようなパターンがあります。
- 生来小食、食事に関心が無いために低体重となる
- 食べ物の味や食感、においなどの感覚過敏のために、偏食で栄養量が十分に取れない
- 食事に関連したトラウマによって食事・飲み込むことが怖くなる
など
摂食障害は特別な病気ではない
摂食障害は特別な人がなる病気でなく、誰にでも起こりうる病気です。
発症のきっかけは、ダイエットやストレス、自己評価の低さ、完璧主義な性格など、人それぞれです。特に、体型や体重に関する社会的プレッシャーや、職場での人間関係、仕事のストレスなどが引き金となり、社会人になってから発症するケースも少なくありません。
「自分の意志が弱いからだ」と1人で抱え込まず、専門的な治療が必要な病気であると正しく認識することが大切です。
摂食障害が仕事に与える影響
摂食障害は、プライベートだけでなく仕事にも様々な影響を及ぼします。
「仕事が辛い」と感じるのは、あなたの意欲や能力の問題ではなく、病気によって心と身体に不調が起きているからです。
集中力・思考力の低下による業務への支障
低栄養状態は、脳のエネルギー不足を招きます。また、「食べ物や体重のことばかり考えてしまう」という強迫観念も、仕事への集中を妨げる大きな原因です。
その結果、資料作成でのケアレスミスが増えたり、上司や同僚からの指示が一度で理解できなかったりと、業務のパフォーマンスが低下しやすくなります。
これが続くと、仕事への自信を失ってしまうこともあり得ます。
深刻な影響と体力的な限界
十分な栄養が摂れていないため、身体は常にエネルギーが足りない状態にあります。朝起き上がるのが困難だったり、通勤だけで疲れてしまったりと、深刻な体力の低下を感じる方が少なくありません。
デスクワークで座っているだけでも強い疲労を感じ、めまいや立ちくらみを起こすこともあります。これは気力の問題ではなく、身体が出している危険信号です。
人間関係やコミュニケーションの悩み
職場での大きなストレスとなるのが、「食事」が関わるコミュニケーションです。同僚とのランチや飲み会を避け続けることで、「付き合いが悪い」と誤解され、孤立感を深めてしまうことがあります。
また、栄養状態の不安定さは気分の波を引き起こしやすく、イライラしてしまったり、急に落ち込んでしまったりと感情のコントロールが難しくなり、周囲との関係に悩む原因にもなります。
欠勤や早退の増加
心身の不調が重なると、どうしても出勤できない日が増えてしまいます。過食嘔吐後の消耗、強い倦怠感やめまいなど、症状によっては出社が困難になることがあります。
欠勤や早退が続くと、職場への罪悪感や「自分はダメだ」という自己嫌悪に陥りやすくなり、それが更なるストレスとなって症状が悪化してしまう、という悪循環が起こるケースも少なくありません。
摂食障害の方が働きやすい仕事・職場のポイント

摂食障害の症状と付き合いながら仕事を続けるには、心身への負担が少ない環境を選ぶことが重要です。
「仕事が辛い」と感じるのは、環境が合っていないサインかもしれません。
この項目では、無理なく働くための具体的なポイントを3つご紹介します。
勤務時間や場所を調整しやすい働き方を選ぶ
摂食障害を抱えていると、日によって体調や気分の波が大きく変わりやすい傾向があります。決まった時間に満員電車で通勤し、決まった時間働くというスタイルが負担になることも少なくありません。そのため、柔軟な働き方ができる職場は、心身の安定につながります。
例えば、出勤・退勤時間を自分で調整できるフレックスタイム制は、朝の体調が優れない日に出勤を遅らせたり、通院のために早く退勤したりすることが可能です。
また、リモートワーク(在宅勤務)が可能な仕事であれば、通勤による体力の消耗を防ぐことができます。
自宅という安心できる環境で、自分のペースで食事や休憩を挟みながら業務に取り組めるのは、大きなメリットと言えるでしょう。
体力的、精神的にフルタイムで働くのが難しい場合は、時短勤務やパート・アルバイトで働く選択肢もあります。
休憩時間を確保できる環境
摂食障害を抱える方にとって、昼休みなどの休憩時間は、リラックスできる時間の場合もありますが、大きなストレスを感じる時間になることがあります。特に、「同僚と一緒にお昼ごはんを食べること」に対して強いプレッシャーを感じる方は少なくありません。
そのため、職場を選ぶ際には、休憩時間の過ごし方が個人の裁量に委ねられているかどうかを確認することが大切です。
例えば、
- 昼休みを1人で過ごしていても、不自然に思われない雰囲気か
- 休憩をとるタイミングや場所がある程度自由か
- 「ランチは全員で」といった暗黙のルールがないか
など
休憩時間の過ごし方が個人の裁量にゆだねられている職場であれば、人目を気にせず自分のペースで食事をとったり、体調が悪いときには横になったりして、心身を休ませることに専念できます。
ストレスの少ない人間関係や業務内容
ストレスは摂食障害の症状を悪化させる大きな要因の1つです。仕事を探す際には、どのような業務内容で、どのような人と関わるのかを意識することが、自分を守ることにつながります。
人間関係の面では、チームで常に連携を取りながら進める仕事よりも、個人で黙々と進められる作業が多い仕事の方が、気疲れしにくい傾向があります。
業務内容については、厳しいノルマや絶え間ないクレーム対応が求められる仕事は、精神的なプレッシャーが大きいため、避けた方が賢明かもしれません。反対に、毎日の業務がある程度決まっているルーティンワークや、マニュアルが整備されている仕事は、先の見通しがつきやすく、安心して取り組みやすいでしょう。
職場に摂食障害を伝えるべき?

摂食障害を職場に打ち明けるべきかは、非常に難しい問題です。「病気を理解してもらえるか」「不利な扱いを受けないか」と悩むのは当然のことです。
伝えることにはメリットとデメリットの両方があるため、慎重に判断する必要があります。
この項目では、判断のポイントと、伝える際の具体的な方法を解説します。
職場に摂食障害を伝えるメリット・デメリット
まず、伝えることの利点と欠点を比較してみましょう。
メリット
- 必要な配慮が得やすくなる
体調不良による急な休みや通院の必要性を正直に話すことで、職場からの理解や協力を得やすくなります。
また、業務量の調整など、具体的な配慮を相談できる可能性が生まれます。 - 隠し続ける精神的負担から解放される
病気を隠すストレスや、嘘をつく罪悪感から解放され、気持ちが楽になる場合があります。
また、その結果、治療に専念しやすくなることもあります。 - 孤立感・孤独感が和らぐ
信頼できる人に打ち明けることで、「1人で抱え込んでいる」という孤立感・不安が和らぎ、精神的な支えになることがあります。
デメリット
- 偏見・誤解を受ける可能性がある
摂食障害に対する理解が不足している方からは、「自己管理ができない」といった誤解を受けるリスクはゼロではありません。 - 過剰な配慮によって居心地が悪くなる可能性がある
周囲が腫れ物に触るような態度になったり、仕事を与えられなくなったりすることによって、居心地の悪さを感じるケースもあります。 - キャリアへの影響に対する不安
今後の昇進や評価に影響が出るのではないかという不安が生じる可能性があります。
誰に、いつ、どこまで伝える?
もし伝えることを決めた場合、次に「誰に」「いつ」「どこまで」話すかを具体的に考えることが重要です。
- 誰に伝えるか
まずは直属の上司に相談するのが一般的です。業務の状況を直接把握しているため、話がスムーズに進みやすいでしょう。
もし話しづらい場合は、人事部や労務担当者、社内にいれば産業医やカウンセラーに相談するのも1つの手です。同僚全員に話す必要はなく、業務上、最低限必要な範囲に留めましょう。 - いつ伝えるか
伝えるタイミングは、欠勤や早退が増えるなど、業務への支障が明らかになった時や、休職を考え始めた時などが考えられます。
できるだけ心身が安定している時に、上司に時間を作ってもらい、落ち着いて話すのが望ましいでしょう。 - どこまで伝えるか
プライベートなことまで詳細に話す必要はありません。伝えるべきは、あくまで仕事に関わる客観的な情報です。
具体的には、「病名」「主な症状」「業務上の具体的な支障」「希望する配慮」「通院の必要性」などを簡潔に伝えるのがポイントです。
伝える前に整理しておくこと
いざ話すとなると、頭が混乱してしまうこともあります。事前に自分の状況と考えを整理しておきましょう。
- 自分の症状と仕事への影響を紙などに書き出す
「週に数回めまいがして集中できない」など、症状が仕事にどう影響しているかを具体的に把握しておきます。 - 求める配慮を具体的にリストアップする
「月2回の通院のために時間休を取りたい」「体調が悪いときは在宅勤務に切り替えたい」など、会社にどうしてほしいかを明確にしておきましょう。 - 医師の診断書を用意する
通院されている場合は、主治医に診断書や意見書をもらいましょう。あなたの状態が治療を必要とするものであることを客観的に証明でき、会社側も必要な配慮を判断しやすくなるため、話がスムーズに進む大切な材料となります。
伝える目的は、一方的に要求することではなく、会社と協力して働き続ける方法を見つけることです。「これからも働き続けたい」という前向きな姿勢で相談することが、良好な関係を築く鍵となります。
仕事を続けるのが辛いと感じたときの選択肢

様々な工夫をしても、どうしても仕事を続けるのが辛いと感じる時もあります。そんな時は、無理して自分を追い詰める必要はありません。
心と体を守るために、「休む」「離れる」という選択肢を持つことも大切です。
無理せず、休職制度を利用する
多くの会社には、病気やケガで長期間働けなくなった従業員のために休職制度があります。これは、会社に在籍したまま、一時的に仕事を休んで治療に専念できる制度です。
休職することで、仕事のプレッシャーから一旦離れ、心身をゆっくりと回復させる時間を作ることができます。
経済的な不安がある場合は、条件を満たせば健康保険から傷病手当金を受け取れる可能性もあります。
休職を考え始めたら、まずは会社の就業規則を確認し、直属の上司や人事部に相談してみましょう。多くの場合、休職の申請には医師の診断書が必要です。
治療に専念するために退職する
職場環境そのものが強いストレスになっている場合や、回復に長い時間が必要だと感じる場合、退職して治療に専念することも前向きな選択肢の1つです。
仕事に関する全てのプレッシャーから解放されることで、症状が落ち着き、回復が早まるケースも少なくありません。
経済的な見通しを立てる必要はありますが、一度リセットして、健康を取り戻すことを最優先に考えるのも大切です。
すぐに次の仕事を探す必要はありません。まずはゆっくり休み、心身が回復してから、自分に合った新しい働き方を焦らずに探していくという道もあります。
摂食障害の方が利用できる公的な支援制度・相談先

仕事や生活に関する悩みを、1人で抱え込む必要はありません。摂食障害を抱える方が利用できる公的な支援制度や、専門の相談窓口があります。
利用できる制度や相談先を知っておくだけでも心の負担を軽減できます。
医療費の負担を軽減する「自立支援医療制度」
継続的な通院が必要な場合、医療費の自己負担額を軽減できる制度です。精神疾患の治療にかかる医療費の自己負担割合が、通常3割のところ1割に軽減されます。
病院の受診費用だけでなく、治療に使う薬代などの自己負担割合も軽減されます。
申請はお住まいの市区町村の担当窓口で行えます。
専門家や当事者とつながれる相談窓口
各都道府県に設置されている「精神保健福祉センター」では、専門家による心の健康相談が可能です。通院していない場合はこちらでの相談から始めてみても良いでしょう。
また、同じ悩みを持つ仲間とつながり、支え合える「当事者団体」や「自助グループ」も各地にあります。まずは身近な保健所や情報がまとめられているポータルサイトなどで調べてみると良いでしょう。
全国の精神保健福祉センターは、下記から調べることができます。
全国の精神保健福祉センター|厚生労働省
摂食障害についての情報は、下記のポータルサイトなどがあります。
摂食障害情報ポータルサイト
安定した就労を目指す「就労移行支援」
障害のある方が一般企業へ就職するためのサポートを受けられる福祉サービスです。職業訓練や仕事探しの手伝い、就職後の定着支援など、安定して働き続けるための支援が提供されています。
利用するためには、障害福祉サービス受給者証が必要です。障害者手帳が無くても、医師による診断書・意見書があれば利用できる場合があるため、詳しくは利用を検討している事業所などに問い合わせてみると良いでしょう。
障害者手帳が無い方が利用できる「WORK! DIVERSITY プロジェクト in 岐阜」

岐阜市にお住まいの方は、「WORK! DIVERSITY プロジェクト in 岐阜」を通じて、就労移行支援を受けることができます。
「WORK! DIVERSITY プロジェクト in 岐阜」は、「働きたくても働けない」「働きづらさを抱えている」といった悩みを持つ岐阜市民を対象に、障害福祉サービスを活用して就労支援を行う取り組みです。
岐阜市内にある「ダイバーシティ就労支援拠点」で、障害の有無にかかわらず、働き続ける力を身につけるための支援を無料で受けることができます。
「ダイバーシティ就労支援拠点」は就労移行支援事業所のほか、実際に働きながら支援を受けられる「就労継続支援A型・B型事業所」も含まれています。
摂食障害の方で、障害者手帳をお持ちでない方でも岐阜市民であれば利用可能です。障害者手帳がない方にとっても利用できる支援の選択肢の一つとして、「WORK! DIVERSITY プロジェクト in 岐阜」への相談・利用を検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ|摂食障害を職場に伝える?無理なく働くためには
まとめ
- 摂食障害は食事のとり方や食行動に問題が表れる精神疾患の1種で、心身に深刻な影響を及ぼす。特別な病気ではなく、ストレスなどが要因で、誰でも発症する可能性がある。
- 摂食障害による集中力低下や極度の疲労は、仕事のミスや人間関係の悪化につながりやすい。自分を責めないことが大切。
- 仕事を探す際は、「リモートワーク」や「フレックスタイム制」など時間や場所の融通が利くか、「休憩時間を1人で自由に過ごせる」環境か、「ノルマが厳しくない」業務内容か、という3つのポイントで選ぶと良い。
- 職場に病気を伝えるか迷ったら、メリットとデメリットを比較・検討しよう。伝える場合は、まず直属の上司に「仕事への影響」と「具体的に必要な配慮」を、医師の診断書を添えて相談すると効果的。
- どうしても仕事を続けるのが辛い時は無理をせず、会社に籍を置いたまま休める「休職制度」の利用や、一度しっかり休むための「退職」も検討を。休むのは気が引けるかもしれないが、回復に向けた前向きな選択肢として考えよう。
- 経済的な不安を軽くなる、医療費の自己負担が1割になる「自立支援医療制度」、就職に向けたサポートを受けられる「就労移行支援」などの公的制度も活用しよう。
摂食障害を抱えながら働くことは、決して簡単なことではありません。集中力の低下や疲労感、職場での人間関係など、目に見えない多くの困難と日々向き合っていることでしょう。
「自分が弱いからだ」「頑張りが足りない」と1人で抱え込み、自分を責めないことが大切です。
心と体の状態に合わせて働き方を工夫したり、職場に理解を求めたり、時には仕事から離れて休む決断をしたりすることは、自分を守るためには非常に重要な一歩です。
この記事で解説した情報が、少しでも心穏やかに過ごせるようになるためのきっかけとなれば幸いです。
この記事に関するお問い合わせはこちらまで:workdiversitygifu@sus-sup.org